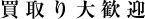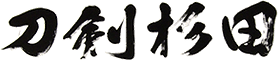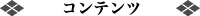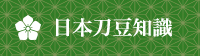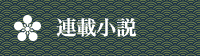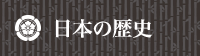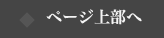「雙」第3回
「雙」第3回 森 雅裕
江戸城の鬼門を守る東叡山は、寛永年間に多くの塔頭が建てられたため、これらを総称して寛永寺という。年号を寺名にするのは延暦寺や仁和寺など由緒ある寺に限られ、江戸では寛永寺が唯一であり、東西にも南北にも数十町に及ぶ境内を広げ、江戸の町を睥睨している。
御前鍛錬を三日後に控え、参加者の顔合わせと打ち合わせが行なわれる日であった。助広の視界にまず現われた知った顔は、山野加右衛門である。
一目も二目も置かれている「首斬り」であるから、入れ替わり立ち替わり、加右衛門の前では挨拶が繰り広げられている。助広には近づき難い雰囲気だった。普通の人間なら、挨拶する方が知らぬ顔を決め込むよりも簡単なのだが、助広はあえて精神的労力の大きい方を選ぶ性癖がある。
しかし、前回、加右衛門に無礼を働いたのは事実である。筋を通さねば――。その思いが何よりも優先した。
「先日は失礼いたしました」
「忘れたな。おぬしも忘れた方がよい」
加右衛門はあっさりしたものだ。人間が練れているというより、世慣れている。無益な出来事は忘れることができるようだ。
「今日は杖をお持ちでないのですか」
武器としても有効だったあの杖だ。助広には気になっていた。
「先日は雨降りだったので、杖を携行した。万一、身に危険が迫った時、雨の中で刀は抜きたくないからの」
助広はその答を予想していた。加右衛門は、刀を濡らさぬこと、鯉口(鞘口)に水を入れぬことを心がけたのだ。ある意味、この男も職人気質だった。
「さて。あらためて、酒席をもうけるか」
「あいにく、不調法でございまして」
「おぬし、虎徹と気が合うかも知れぬな」
「え……?」
「あの男も酒は飲まぬ」
刀鍛冶で下戸、というのは珍しいかも知れない。
「そのくせ、奴の仕事場には枡がいくつも転がっている」
「枡……ですか。御覧になったのですか」
「おお。奴も相手によっては飲むのかも知れぬな」
「虎徹を……御存知なのですね」
「江戸の主立った刀鍛冶なら、皆、わしは知っておる。どのような刀が折れず曲がらずよく斬れるものか、誰もがわしに尋ねるからの。わしの方から仕事場を見ることもある」
虎徹を個人的に知っていながら、伊達家が依頼した虎徹銘の――個人作ではないかも知れないが――脇差の試し斬りを行なわなかったのか。この男には、人のつながりよりも経済が優先するのか。
「虎徹に興味があるか」
加右衛門は唇の片方を吊り上げるような笑いを見せた。
「今日、来ておるぞ」
「え……?」
「虎徹も御前鍛錬を行なう」
「あ。江戸からの参加は、安定師と虎徹師、お二人ですか」
「将軍家お膝元ゆえ、それも当然であろう」
将軍家には、今は三代目となっているお抱え刀工の越前康継がいる。しかし、御前鍛錬には刀鍛冶たちの競争という意味合いもあり、幕府工を江戸の代表とするわけにはいくまい。上総介兼重も江戸在住ではあるが、津藩工という立場上、人選からはずれる。
「安定や虎徹よりもっと若い者を、それも彼らのごとき同門ではない刀鍛冶を選ぶべきだと、わしは腰物奉行に進言したが、今回の人選には、もっと上の意向が働いたようだ」
「もっと上……」
それが幕府のどのあたりを指すのかも心にひっかかったが、
「安定師と虎徹師は同門なのですか」
その方が助広には興味深かった。安定はそんなことはいっていなかった。
「同門のようなもの、というべきか。江戸鍛冶の多くは直接と間接の違いはあれ、越前がらみでつながっておる。康継も兼重も安定も虎徹も越前出身ゆえ」
彼らの作風には似通ったところがあり、合作など交流の記録も後世まで残されることになる。したがって、師弟関係は混乱している。
「そういえば、おぬしが受領しているのは越前守だな。名前だけは彼奴どもの親玉だな」
確かに。越前という土地が徳川一門の領地で、格式も文化水準も高いことがこうした職人たちにも影響しているのだ。
しかし、その親玉にしては、
(まったく、俺は何も知らんわ……)
助広は取り残された気がした。
もちろん、越前派閥ばかりが江戸鍛冶ではなく、刀工の数では近江守正弘を筆頭とする法城寺派が最大であり、この時代には少ない備前伝丁子刃を焼く近江出身の石堂派など、有力な刀鍛冶は他にもいる。
「山野様は、安定師、虎徹師の実力をいかにお考えですか」
「買っておるさ。いや、買ってくれたのは向こうかな。両名とも、わしにだいぶ金を使ってくれたからの」
「優劣をつけるとしたら……?」
「虎徹が上だ」
「それは虎徹師がより金を使ったということですか」
加右衛門は目を細め、その奥を隠すように笑った。
「助広殿。不調法などといわず、気が変わったら、いつでも拙宅を訪ねられよ。その気にならぬ刀鍛冶はおらぬ」
寛永寺に東都随一といわれる根本中堂が建立されるのは元禄十一年(一六九八)のことだから、まだその壮大な姿はない。しかし、承応三年(一六五四)、尊敬(守澄)法親王が入山して以来、事実上の天台宗総本山であり、将軍家菩提寺の性格も帯びているだけに、上野の山を埋め尽くすどの建造物も壮麗を競うものであった。
これでも一部は三年前の明暦の大火で罹災しているのだが、市内各地で焼失した寺院の多くが移転してきたため、東叡山全山の規模は以前よりもむしろ大きくなっていた。
寛永四年建立の法華堂の中庭に御前鍛錬の準備が進められていた。鍛冶屋によって、設備の使い勝手は違うが、ここまでは江戸鍛冶が指図したようだ。鞴と火床が五基据えられて、雨風を避けるためだけの簡素な板壁と屋根が、大工たちによって、設えられている。
「まるで、長屋の惣後架(便所)だな」
そんなことを呟いたのは、およそ刀鍛冶らしからぬ愛敬に満ちた若者だった。
「お前様も刀鍛冶かね」
「大坂の助広と申します」
「これは御丁寧に……」
苦笑いをこぼした。よく動く目が妙に人なつこい男だ。助広のような無愛想には、どういうわけか、こういう人物が近づいてくる。
「俺は奥州会津の山猿だ。長道という」
「では、陸奥大掾殿ですか」
「よしましょう、そんな呼び方」
「では、長道殿」
「やめてほしいのは、『殿』をつけることだが」
「…………」
のちに「会津虎徹」と賞讃される業物刀工だが、本家の虎徹自身がまだ無名である。初代長道もこの年、二十八歳にすぎない。しかし、すでに万治元年、陸奥大掾に任じられている。初銘は道長だったが、受領の際の口宣案に長道とあったので、そのまま長道にあらためたという。
後年、長道は助広の弟子筋にあたり、受領の推挙も助広によるものだという巷説が生まれるほど因縁浅からぬ二人である。しかし、助広は以前から彼の名を知っていたわけではない。今日、寛永寺へ来て、ようやく参加する刀鍛冶の名前だけ聞いたのである。
「ここに火床が五つ……ということは、刀工も?」
「五人だ。そんなことも知らないのかね。大坂の刀鍛冶は世間離れしているな」
大坂の刀鍛冶ではなく、助広が世間離れしているのである。
「肥前佐賀からは三代忠吉。あそこで、大工たちにうるさく注文をつけているでかいのがそうだ」
精悍さと朴訥さが同居する背の高い男だった。忠吉は江戸初期の巨星・初代忠吉(武蔵大掾忠広)の孫である。父は近江大掾忠広。この父も名工だが、若き忠吉はそれを凌ぎ、祖父と肩を並べる腕だと声望が高い。この年の十月には、この三代忠吉も陸奥大掾に任じられ、翌年には陸奥守を受領することになる。助広と同年の二十四歳である。
「将軍家お膝元の江戸からは、大和守安定」
すでに見知ったその安定は、弟子たちに指図して、火床に炭粉を敷き固め、高さを調節している。
「そして、長曽祢興里――虎徹だ、あれが」
その男は、入道と称するのだから剃髪していた。小さな顔に大きな目が鋭く、口許に生気を漂わせ、表情の隅々に意志の強さを年輪のように刻んでいる。引き連れた弟子たちは動きに無駄がなく、いかにも優秀そうだ。
「虎徹師匠があのようなお歳とは思わなかった」
越前の甲冑師から転身したというのだから、若いとは思っていなかったが、五十歳を越えているように見えた。
「そうかね。俺はむしろ若いと思うが」
「若い……?」
「虎徹の作刀には、『至半百居住武州江戸』とやら添銘したものがあって、刀工を志して江戸に出たのが五十歳と称しているらしいが……。さて、どうかな」
「どうかな……とは?」
「甲冑師だから鉄の鍛錬は習熟していたとしても、刀剣の修業はまた別だ。五十歳から江戸で何年も修業したにしちゃ、若くないか、あの様子は」
「ふむ。独自の年齢の数え方をお持ちのようだ」
「独自なのは年齢だけかな」
「どういう意味です?」
「虎徹には、もっと妙な噂もある」
「それは……?」
「迂闊なことは会津の山猿ごときの口からはいえぬよ。江戸の刀鍛冶から聞け」
「…………」
「ともあれ、あの師匠、なかなかの宣伝上手だと俺は見ているがね」
「長道殿」
「よせ、といった。藤四郎で結構だ」
「素人(トーシロー)……?」
「ふざけた名前だが、三善藤四郎というのが通称だ」
鎌倉期、粟田口派の名工・藤四郎吉光にちなんでいるのか。何にせよ、そうすぐに呼べる助広ではない。
「私は、あの虎徹師によく似た人物を知っている」
「ほお。どこの何者だね?」
「以前、大坂にいた近所の金工だ」
「なるほど。忘れ難い面魂ではあるな」
法華堂の広間へ集合の声がかかり、端座した刀鍛冶たちの前に腰物奉行が現われた。ようやく、参集した彼ら五人が正式に引き合わせられた。各地を代表する刀工たちである。ただ虎徹だけが異質だった。名門の嫡流でもなければ、官位も得ておらず、有名でもない。しかも最年長である。
(宣伝上手と長道はいうたが、そればかりではなさそうやなあ……)
法華堂から再び内庭へ下りると、関係者たちの人垣越しに、助広は盗み見るように虎徹の様子をうかがっていたが、ふと視線が合ってしまった。逃げようとしたが、なにしろ弟子も連れず、孤独な助広には、行き場もない。虎徹の方から近づいてきた。先刻、名乗りだけは互いにあげている。
「助広殿……だったな」
「あ。お見知りおきください」
「場違いな刀鍛冶がいると、お思いのようだが」
「いえ。知人に似ていらっしゃったもので、つい……。失礼いたしました」
「ほお。知人……」
「長曽祢興光という名前を御存知ありませんか」
「弟だ」
虎徹は、あっさりといってのけた。
「鍛冶の仕事をせず、切り物師として、大坂で開業していた」
「はい。十年ほど前に江戸へ出られましたが」
「うむ。わしの近くに住んで、行き来もあったが、死んでしもうた。明暦の大火の翌年――今より二年前の春だった」
「あ……。左様でしたか」
「同じ頃、わしも病を得てな、面変わりがしたといわれるのだが……興光はわしに似ていると思うか」
「はい」
助広が知っているのは十年より以前の興光である。その子供とは幼馴染みといえる。しかし、親の方は、職人仲間とはいっても、助広はまだ少年だったし、社交性にも乏しいから、記憶に曖昧な部分があるかも知れない。が、同一人かと思うほど似ている。
「双子だ」
虎徹は、そういった。目つきも口調も穏やかで、引き込まれるものがある。しかし、つけ入る隙のないきびしさも含んでいる。常人なら隠居の年齢で刀工を志したというのも、この人物なら有り得るかも知れない。
助広はこの男に珍しく、会話に意欲的となった。
「興光師の一作金具で拵えた脇差を持っております。法華堂の控えの間へ置いてありますが……」
今は腰物奉行の前に出るので、儀礼用の黒一色の脇差を帯びている。
「ほお。見たいものだな」
「では――」
「拙宅へお持ちにならぬか。池之端だ。ここから目と鼻の先だ」
「あ」
人づきあいは苦手だとばかりはいっていられない。
(虎徹とは、どれほどの刀工か)
研究心と好奇心が、助広の孤独癖に勝った。
「では、お邪魔させていただきます」
池之端を吹き渡る風が、鉄の風鈴を打ち鳴らしている。軒下に揺れるその風鈴へ手をのばし、
(器用なもんや)
助広は感嘆した。鋳造ではなく鍛造となると、鉄板を赤めながら叩いて、釣鐘状にしぼるのだから、簡単ではない。
(鉄味もええ)
錆が見事な黒紫色だ。いい鉄を使っているということか――。
母屋と鍛錬(鍛冶)場が向き合う内庭へ案内され、助広は縁側の風鈴に見入った。こんな風鈴にもほほえましい銘がある。だが、「長曽祢興里」でも「虎徹入道」でもなく、「止雨」とある。
(山野加右衛門様と一緒におった菓子師や……)
その菓子師の名前がどうしてここに刻まれているのか、助広には疑問だったが、この男の性格で、口には出さない。
虎徹はその風鈴がささやく縁側に庭先から腰を掛け、助広が手渡した脇差に見入っている。視線は興光の金具よりも助広の刀身にこそ向いていた。安定がそうだったように。
「よい地鉄だ。江戸では、南蛮鉄が全盛でな。御公儀が鉄砲作りのために大量に輸入したものを康継が刀作りに使って以来、猫も杓子も『以南蛮鉄』と銘を切るようになった」
「私のその脇差も南蛮鉄を使っています」
「ほお。大坂では江戸よりもよい南蛮鉄が入手できるようだ。江戸鍛冶の刀は、これほど地も刃も明るく冴えぬ」
南蛮鉄はインド産のウーツ鋼に類するものだが、寛永十六年(一六三九)の鎖国以降、まとまった量の供給は絶えている。貴重な輸入鉄だが、産出地によって、品質に差がある。
「刀鍛冶の腕はいい鉄をいかにうまく処理するかにかかっている。悪い鉄は名人にもどうにもならぬ。御前鍛錬でも南蛮鉄を使うのか」
「はい。下鍛え済みのものを持参しました」
「なるほど。鍛錬ぶりを見られたくないか」
「いえ。南蛮鉄そのものも持参していますから、鍛錬もやります」
「以前は海の向こうへのあこがれから、南蛮鉄も重宝されたが、今は冴えぬ刀を作る言い訳にすぎぬ。南蛮鉄を使うのは助広殿の勝手だが、銘にはそのことをうたわぬことよ」
「…………」
「いや。よけいな口出しだったな」
「虎徹師匠」
助広は、胸にひっかかっていた質問を切り出した。
「興光師は亡くなられたということですが、御家族はいかがなされたのでしょうか」
「妻は大坂で死んでいる」
それは助広も知っている。妻の死後、それをきっかけとしたかのように、すぐに江戸へ下ったのだ。
「娘さんがいらっしゃいましたが……」
「妻の連れ子だった娘だな」
「それは私の知らぬことですが」
「このあたりにはおらぬ」
意味がわからない。確かめようとしたが、虎徹は背を向け、縁側を離れている。
「仕事場を御覧になるか」
鍛錬場へ招かれた。
弟子たちが作業中だ。邪魔にならぬよう、肩をすぼめながら観察した。奇抜な造作でもなければ、変わった道具があるわけでもない。が、生気を感じる仕事の場だ。
(できる……)
そう直感させるものが漂っている。
鍛錬場の隣の建物は板の間になっていて、框を上がると、刀剣の仕上げに使う工作場らしく、鍛冶押し(荒研ぎ)用の研ぎ台が据えられている。
鍛冶押しなどほとんどやらずに研師へ回してしまう刀鍛冶もいるが、それでは姿形を決めるのは研師になってしまう。虎徹はしっかり下地まで作る方針らしい。
荒砥がかけられた刀を手に取り、光に当てると、互ノ目が整然と並んだ刃文が浮かぶ。しかし、単調ではなく、足が刃先へ抜けそうなほど深く入り、沸えが強い。
「数珠刃とわしは呼んでいる」
虎徹は、いった。安定のところで見た脇差とは雲泥の出来だ。研師に預ける前のこの段階では、地鉄のよしあしまではうかがえないが、刃がこれなら、地鉄も凡庸ではあるまい。さすが、御前鍛錬に選ばれる技量ではある。
「数珠刃……ですか」
「もう少し高低のついた瓢箪刃をさらに進化させたものだ」
安定のところで見た例の脇差がその瓢箪刃だった。
「沸えづいたのたれ調の互ノ目を連ねるのが江戸のこれからの主流だ。もっとも、数珠刃のさきがけは上総介兼重だ。しかし、いずれ世間はそれを忘れる」
虎徹の方が技量が上なら、確かに世間は兼重よりも虎徹に目を奪われるだろう。