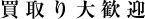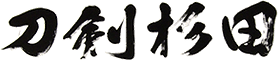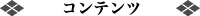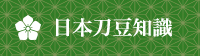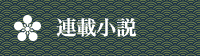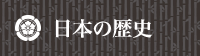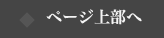抜けた鬼鍾馗 第一回
抜けた鬼鍾馗 第1回 森 雅裕
奈良系の金工集団は後藤系、橫谷系と並んで彫金界の三大門閥を形成した。奈良の流名を許された一門は数十人にも及ぶ。奈良本家は江戸前期の奈良利輝を家祖とするが、元来は建築金物などを制作する錺職であったといい、刀装金工としては二代目の利宗を初代と数える。町彫りの基礎を確立し、もっとも傑出していると見なされているのは金工二代目の利治であり、一派を隆盛に導いたのが金工三代目の利永である。
以後も代を重ね、分家、分派を生み、自分の流派を打ち立てる名人たちも輩出し、奈良の名跡は廃れても、そうした末流は幕末まで続いた。
奈良心春がその鐔を見せられたのは上野の芸大の研究室だった。鉄地で、鍾馗から逃げる鬼が橋桁にしがみついて隠れている。ありがちな画題ではある。しかし、鬼の泣きそうな表情に愛嬌があり、鬼を探す鍾馗もまた困り顔で途方に暮れているのだ。江戸の彫金師にこんな表現力があったとは意外だった。
銘は武州江戸住奈良小左衛門作。小左衛門は奈良派の本家が襲名する名乗りである。
「お前の遠祖だろ」
と、見せてくれたのは彫金の講師・岩本琴太郎。建前上の指導教官である教授は講評の時に顔を出す程度で、普段の指導者はこの講師である。江戸中期から後期にかけての名人・岩本昆寬の末裔と称している。
岩本家は町彫りの代表格である橫谷・奈良派の長所を取り入れ、洒脱な江戸前の作風が特徴だ。とはいえ、岩本琴太郎は現代の彫金家らしく刀装具などはほとんど作らず、商売っ気のあるジュエリーも作らず、ホテルのロビーや美術館に飾るような置物の制作が多い。この男は心春とはひと回り年が違うが、金工の家に育った者同士で、幼馴染である。
心春は彫金科の学生だ。鐔を一見して、奈良派二代目の利治あるいは三代目の利永かな、そう思った。ただの勘だ。江戸彫金界の名人といわれる奈良利寿はこの二人に師事したとする説が有力だ。師匠とはいえ、彼らは利寿ほどの技量ではない。だが、この作は抜きん出ている。
「面白いね。ちょうだい」
「やるか。今度、美術館に展示するんで持ち主から大学が借りたんだ。お前の遠祖の作だから見せてやった。これから図録に載せる写真の撮影に回す」
芸大には撮影機材を揃えた写真センターが設置されている。必要な写真は自前で用意できる。
芸大付属の美術館では半年後に「鬼神展」を開催する。美術に描かれた鬼神の特集である。美術館の企画は二、三年前から準備するのが普通だが、予定が変更されることも珍しいことではない。鬼神展もそれなりに時間をかけているが、この鐔の展示は最近になって急遽決まったものらしい。予定変更は美術館も慣れたもので、事情をいちいち詮索しない。
この鐔には不釣り合いな赤銅覆輪がかかっており、岩本琴太郎は疑問を口にした。
「耳の覆輪は後補のようだが、鉄地が朽ち込んで補修したのかな」
「朽ち込んだ様子はないわね。鐔全体の形も崩れてない。なんでこんな余計な覆輪をかけたのか、謎ね」
ミスマッチだが、うまく嵌め込んである。
「あえていえば、彫刻に比較して鉄地の部分が小さいような気もする。覆輪をかけるために鉄地の周囲を削って整形したとも考えられ……」
いいかけた琴太郎の鼻先に心春は鐔を突きつけた。
「はずれたよ」
「え……?」
心春の左手に鉄の鐔、右手に赤銅の覆輪がある。
「おいっ。がっちり嵌まっていたはずだぞ。何をしたんだ?」
「別に。どうやって嵌め込んだのかなあと撫で回していたらストンと取れた」
「そんなアホな……」
琴太郎は戻そうとしたが、鐔と覆輪のサイズにまったく余裕がなく、合わない。
「そんなことより、これ見て」
覆輪がはずれた鉄地の耳には金象眼が施してあった。崩し文字である。まるでこの文字を隠すための覆輪のようでもあった。心春は平仮名だけ拾い読みした。
「……の、り、さけ……読めない」
「お前という奴は……」
琴太郎は数文字で内容を理解したらしい。
「天の原、ふりさけ見れば春日なる、三笠の山に出でし月かも」
「ああ。高校一年の時、国語教師が明日までに全部暗記してこなきゃ痛い目に遭わすぞと恫喝した百人一首にそんなのがあったような気がする。ろくな教師に出会ってないから私は大学で教職課程も取らない」
「たいした心がけだが、では、これが阿倍仲麻呂の歌だということはわかるだろう」
心春は挙手して応えた。
「もちろんですっ。玄宗に重用された遣唐使ですわ。私は勉強はできないけど教養はありますっ」
刀装具は故事伝説を題材とすることが多いので、歴史の知識は持っている。かなり偏ってはいるが。
琴太郎は首をかしげた。
「この文字は布目象眼で入れてある。覆輪をがっちり嵌め込めば、こすれて傷つくか剥落してしまいそうなものだが、全然傷ついてない。昔の職人仕事はどうやったのか謎のものもあるにはあるが……」
「この覆輪は私が難なくはずしてしまったように無理なく嵌め込むことができたのかも」
「そんなこと、普通の金工には無理だ。お前みたいな変態ならともかく……」
「じゃあ、変態の力で戻してみようか」
心春が鐔と覆輪を合わせようとすると、
「待て待て。せっかく隠されていた和歌が現れたんだ。持ち主に報告して、この状態で美術館に展示するかどうかを相談する。
「お好きなように。キンタロウさん」
「コトタロウだ」
琴太郎をキンタロウと呼ぶのは子供の頃からの習慣だ。
「変態は帰りますっ」
言い残して、心春は美校をあとにした。
この娘は通学にギターケースを背負っている。アコギではなくエレキである。普段から音校の練習室を使っている。ギターはクラシックで使う楽器ではないから芸大にギター科などない。あれば、心春は入学しただろう。芸大はアカデミックな教育の場ではあるが、教官も学生もクラシックにこだわらない。ロックも演歌も同じ音楽として尊重するのが本物の音楽家だ。
やむなく美校の彫金科に入学したが、美校と音校は道一本を隔てて向かい合っており、互いの空気は環流している。音校内の楽器練習室はネット予約することになっており、学生数に対して部屋数は不足がちだが、時期や時間帯によっては空いている。使っても文句をいわれたこともない。
心春は音が外に漏れないヘッドホンアンプで練習することが多いが、バンド演奏の音源を再生しながら練習する場合もあり、芸大らしからぬヘヴィメタ系のサウンドが鳴り響く。最初の頃は「何者だ、あいつ」という目で見られることもあったが、今は教官たちからもその実力に一目置かれている。
心春の自宅は葛飾柴又にある。葛飾区はかつては日本刀関係の一流職人が何人も住んでいる地域だったが、高齢で亡くなったり、再開発のために立ち退いてしまったりで、今ではさびしくなってしまった。元々理由があって職人たちが集まったわけではなく、偶然であったらしい。奈良家もそのひとつだった。だが、父の奈良左絵門は奈良家の出ではない。東京芸大彫金科の貧乏学生だったが、練馬石神井にあった学生寮で母と出会った。母こそが奈良家の娘で、ヴァイオリン学生だったが、音の問題があるから柴又の実家を離れて寮生活していたのである。二人は卒業後に結婚して、父が奈良家を継いだ。左絵門というレトロな名前が奈良家歴代が襲名する小左衛門に似ているのが祖父に気に入られたらしい。奈良家は女系家族で、彫金の伝統も途絶えかけていたが、養子の左絵門によって、なんとかつながったのである。
とはいっても、母も祖父もすでに亡くなり、左絵門と心春の父娘暮らしである。すき焼きといって食卓に出るのが牛丼であるような家だ。
住居と仕事場はつながっているが、両方に玄関があり、出入りに使うのはほとんど仕事場の方である。仕事場には父娘それぞれ専用の作業机がある。一見すると、二人とも乱雑に道具類を散らかしているが、本人だけにわかる秩序がここには存在する。
「ちゃんとするな。そんな奴が作ったもの、誰も見ない」
心春は左絵門からそう教育された。そうはいいながら、真面目さから脱却できないのが左絵門だった。
「御先祖の鐔を大学で見たよ。鬼鍾馗の図」
そう報告すると、父は読んでいた「パタリロ西遊記!」を置いた。
「奈良派の鐔は江戸の町彫りとしては人気だったが、格調がどうのこうのいわれて芸術性は今いちとされている。そんなもんを芸大が有難がるのか」
「美術館で展示するらしい。鬼神展だって。小左衛門さんにしては面白い作だった。ひょっとするとひょっとして、名人利寿の代作かも」
利寿は奈良派の門人筋だが、娘を奈良本家に嫁に入れており、その末裔が現在に至っている。つまり、心春である。
「鬼鍾馗とは……鬼と鍾馗の隠れんぼか」
「うん。奈良派には珍しくもない画題だけど、鬼と鍾馗さんの表情が……」
「どちらも奇妙な困り顔か」
「奇妙なのは耳に赤銅覆輪が嵌め込んであることも。なんであんなことしたのか、違和感がある。はずれちゃったけど」
「はずれた? はて。しっかり嵌まっていたはずだが」
「何よ。知ってるの?」
「うーん」
「なんでかわからないけど、私が触ったらあっさりはずれたわよ」
「それが一番奇妙だな」
「とーちゃん」
心春は父の顔を覗き込んだ。
「正直に話しなさい。怒らないから」
「実はな……昔から奈良家に伝来していた鐔だ」
「あらまあ」
「お前が小学生の頃、売り飛ばした。出入りの骨董屋だ。どこへ転売したかは知らん」
「御先祖が嘆くわよ」
「お前のかーちゃんが死んで、何もかも嫌になってた時期だ。俺だけじゃなくお前も落ち込んでた。気分転換にとその金でギターを買ってやった」
「どういう発想なのかね。理解に苦しむ」
「かーちゃん亡くしたお前は、公園に誰かが忘れていった一輪車を一日中練習してたんだぞ。やばいぞこいつ、と心配になるだろ」
心春の母は在京オーケストラのヴァイオリニストだった。心春も幼い頃に少しだけ手ほどきを受けた。なのに、左絵門が娘に違う楽器を与えたのは「思い出させないため」だという。本当は自分が思い出したくなかったのだと心春は思っている。
どうせ楽器を修業するなら、心春にしてみればピアノの方がよかったのだが、
「持ち運びできない楽器は生活環境が変わったら続けることができない。何年も修業したのが無駄になる」
それが若い頃から貧乏生活を続けてきた左絵門の持論だった。しかし、ギターは独習でも上達するが、ヴァイオリンやピアノは教師につかないと上達しにくい。金がかかるのである。それもまた理由だっただろう。
心春は左絵門の作業机を見やった。鐔の下図を描いている。銀座のギャラリーで現代刀職者の作品展を開催することになっており、その準備だが、まだ下図の段階から進捗していない。美術館博物館の企画と違い、準備期間は短いのだが、絶望的なほど遅れている。間に合わなければ、旧作を出品することも有り得るが、新作は現代の奈良派の作として中国故事を題材にする予定で、下図は中国王朝の貴婦人だ。武具の図柄には珍しい。
「何? これ」
「虞美人だ」
「なら、『パタリロ西遊記!』じゃ参考にならないやね。宝剣・青峰をふるう剣舞でもさせたら?」
「お、いいね。お前、作ってくれよ」
「そんな暇ない」
父は下手ではないが格別の腕でもない。腕がどうであれ、今どき刀装具だけでは生計が立たないことは岩本琴太郎と同様だ。ただ、芸術家気質の琴太郎とは違い、左絵門は雑多な装飾金具やアクセサリーなども手がけている。彫金のセンスは心春の方が上で、鳶が鷹を産んだと世間は評している。もっとも、心春には彫金で身を立てる気はない。
「三、四日、京都行ってくる」
「仕事か」
「バンドのライブ」
「お前にギターを与えたのは正解だったのか失敗だったのか、考えるよなあ」
「安物だったけどね。伝来の鐔の代金で買ったにしては」
「それでも大喜びで抱いて寝てたけどな。可愛いもんだったぞ、あの頃は」
むろん、今はもっといいギターを何本か自力で買っている。敬愛するギタリストを訪ねて、教えも受けた。
「今だって可愛いでしょうが」
「幼稚園の頃には、可愛いではなく格好いいといわなきゃ喜ばなくなったけどな」
「どっちでも喜ぶよ」
「可愛いくて格好いいよ、お前は」
「えへへへへ」
こういう父娘である。
翌日、バンド仲間の才喜すみ花と東京駅で落ち合い、京都へ向かった。すみ花は芸大のヴァイオリン学生である。ロックバンドにヴァイオリンの参加は異色のようだが、特に珍しいわけでもない。
すみ花との出会いは入学した年の芸祭(学園祭)だった。美校音校の各科一年生が組み、グループごとに張りボテの御輿を作って上野公園内をパレードするのが毎年の行事である。彫金とヴァイオリンは別のグループだったが、御輿制作の現場では互いに顔を合わせることもあった。しかし、心春は学内ライブ出演のためパレードには参加しなかった。
学内ライブのあと、声を掛けてきたのが才喜すみ花だった。この日、ディープパープルの難曲を数曲披露したのだが、
「ジョン・ロードのキーボード・パートまでギターで弾きまくるなんて、すごいね」
と、すみ花はハードロックに理解があることを示した。しかも聞く者の脳が溶けるような甘い声だ。
「あんなに楽しそうに弾く人、初めて見た」
「あなたは楽器やってて楽しくないの?」
「ヴァイオリンは可愛いと思ってる」
「可愛い?」
「うちは音楽一家だったから当然のように楽器始めたの」
そういう「当然のように」世襲する学生が音校にはまま見られる。
学内ライブは学生仲間と組んだ芸祭限定のステージだったが、学外では心春はプロと組んでいる。
「私もバンドやりたいな」
「やりゃいいじゃない」
「仲間に入れてくれる?」
「いや。そういう意味じゃなくて……」
面倒臭そうだから避けようとする心春だったが、芸大は狭い学校なので、次第に言葉を交わすことも増える。おかしなもので、数日顔を見ないと、どうしているのかと気になる。
何でも「可愛い」で表現し、楽器を嫁入り道具と考えている音校には珍しくもないタイプかなという第一印象だったが、後日の学内演奏会で彼女が弾くパガニーニを聴き、半端な才能ではないことを知った。こんな才能の持ち主に「一緒に練習しようよ」とアタックされると無下にもできない。
「心春に合わせてエレキバイオリン買ったんだよ」
「それ、私のせいか?」
「エレキバイオリンは骨組みだけでボディはスカスカだから、アコースティックより軽いかと思ったら意外に重かったよ」
「あなた、ロックバンドの沼にはまっちゃったら、親や先生に叱られないの?」
「父はなんでも屋みたいな音楽家だからジャンルにこだわらないし、母はもう死んじゃった。芸大の先生は生徒の人生に干渉しない。それがこの学校」
それはそうだ。そんな経緯があって、すみ花は心春が参加しているバンドのライブにも出入りするようになった。プロのバンドである。
ある時、ライブハウスのスピーカーが「飛んで」しまったことがあった。キーボード奏者がコンプレッサーの設定を勝手にいじったとかいじってないとか店側の音響担当者と大声で揉めているのを尻目に、すみ花がヴァイオリンでキーボードのパートを弾き始め、誰もを唖然とさせた。
心春もキーボードのパートをギターで弾くことがあり、その怒濤の技巧を驚愕されたりあきれられたりするが、宮地のヴァイオリンは甘く周囲を包み込み、それでいて芯の強さもある。
メンバーはあっさりと彼女の虜となった。
「前々からヴァイオリンのメンバー欲しいと思ってたんだ」
「嘘つけ」
心春は吐き捨てるように呟いたが、それ以来、すみ花は不定期で助演しており、二人は「混ぜるな危険コンビ」と呼ばれている。
芸大は美校も音校も実技最優先であるから授業の出席率など問題にされない。むしろ皆勤の学生などは教官から「何か目的があるのか」と怪訝な顔をされてしまうほどだ。
今回のライブハウスは北野天満宮の近くだった。
「行ってみようよ、天神様」
京都に前乗りした翌朝、ホテルで同室だったので、すみ花は寝起きの心春の髪をいじりながら誘った。心春は手鏡を自分の前に置き、されるがままになっている。
「私は下鴨神社の方がいい。音守とかいう音楽家向けのお守りをゲットしたい」
「北野天満宮から下鴨神社はバスで三十分くらいだよ」
「充分遠い」
「今さ、鬼を斬ったとかいう名刀が展示してあるらしいんだ」
「有難がるのはアニメかゲームのファンでしょ。私は二次元にはまったく興味がないっ」
「心春さあ、ジャネーの法則って知ってる?」
「何それ」
「時間の心理的長さは年齢に反比例するという法則。人は年を取るほど時間の流れを早く感じるようになる。新鮮な経験をすればその印象が強く残って時間を長く感じるけれど、変化のない慣れた生活を続けていると時間を意識しなくなり、あっという間に時が過ぎていく。だからね、充実した人生には好奇心とかチャレンジ精神とかフレッシュな気持ちが大切ということ」
「それはどうかな。ジャネーさんとやらには悪いけど、子供の頃の方が日々の変化もなく漫然と過ごしていたと思うんだよね。家と学校と習い事しかない生活なんだから。子供には見るもの聞くものすべてが新鮮だといっても、たかが知れてる。大人になってからの方がやることいっぱいあるし、行動半径も広がって見聞も深まってるよ。名刀見て、フレッシュな気持ちになるかなあ」
「刀の小道具作ってるんでしょ。何かインスピレーションが湧くかも」
「うーん。……それはいいけど、私の頭で遊ぶな」
すみ花は心春の黒髪で奇妙な団子を頭頂部に高々と捻りあげている。結局、その頭で北野天満宮へ出かけた。
菅原道真を祀った天神社の総本社「北野さん」は外国人の観光客であふれ返っている。灯籠が並ぶ石畳の参道を進むと、楼門の先は緑に囲まれ、平安の空気が満ちている。参拝者を迎えるのはきらびやかな三光門である。
門を潜りながら、すみ花は装飾を見上げた。
「三光というのは太陽と月と星を指すんだけど、この門には太陽と月の彫刻があっても星はない。だから星欠けの三光門というんだって」
「だったら最初から二光門とすればいいじゃん」
「星は不動の北極星なのであえて彫らなかったと……」
「なるほど。この三光門こそが宇宙の中心ってか」
そのような彫刻よりも建築を装飾している金具に注目してしまうのは彫金家の性だ。技術や方法を無意識に考察するし、表面処理にムラなどあれば気になる。
外国人観光客から話しかけられるのを適当にやりすごしたり、カメラマンを頼まれたりしながら玉砂利を踏み進むと、目前に迫る天満宮の本殿はさすがに荘厳な桃山建築だ。回廊には吊り灯籠と欄間彫刻が整然と並んでいる。
「鳴くかとて聞きにきたののホトトギス」
心春はあでやかな色彩の装飾を見上げながら呟いた。すみ花がにこやかに首をかしげた。
「『か』とか『とて』とか『なら』とか『でも』なんて人を疑う言葉でよくないよ。鳴け聞こう聞きにきたののホトトギス」
「するとホーホケキョという鳴き声が……」
「ホトトギスはホーホケキョなんて鳴かないよ」
「ここの境内は梅だらけだよ。梅にはウグイスでしょ」
「実際は梅の木にやってくるのは蜜を吸うメジロであって、ウグイスじゃないらしいけど」
すみ花のこういう妙な知識も心春と波長が合う理由だった。